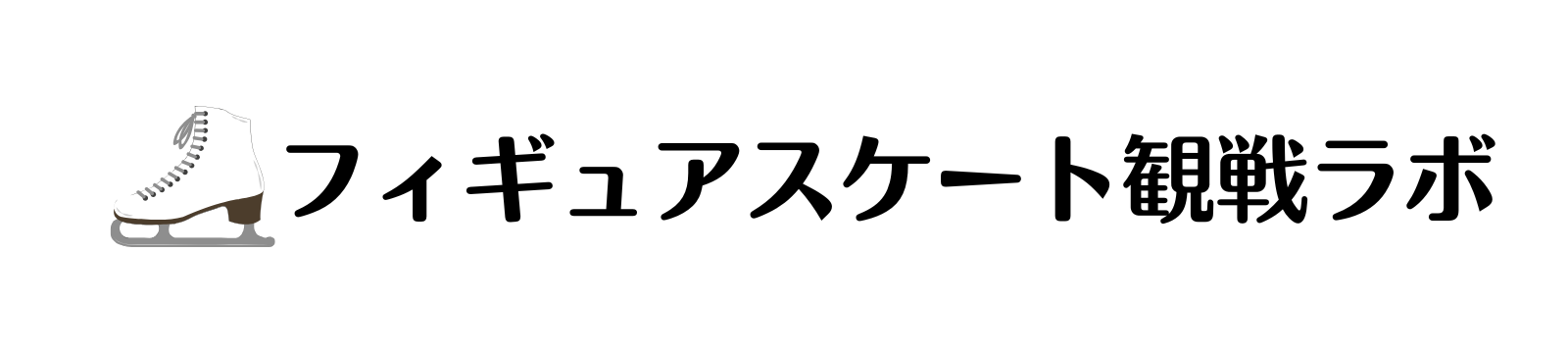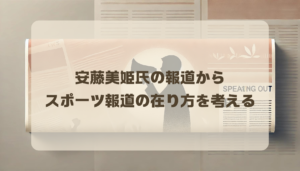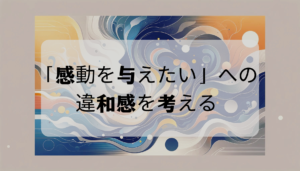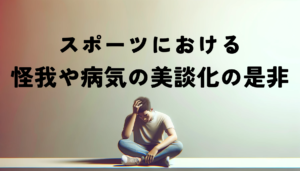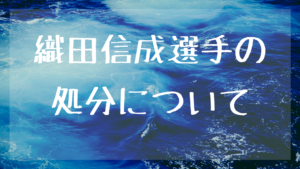近年、フィギュアスケートにおける「観客動員数の減少」や「スター不在による人気低下」がさまざまなメディアで取り上げられるようになっています。一方で、仮にフィギュアスケート人気が低下しているとしても、スター選手の不在をその原因とする論調に違和感を覚える人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、筆者自身のフィギュアスケート現地観戦時の体験をもとに、「本当にフィギュアスケート全体の人気は低下しているのか?」「スター不在が原因なのか?」といった疑問について考察してみたいと思います。フィギュアスケートファンの方はもちろん、新たにフィギュアスケートに興味を持ち始めた方にも、現在のフィギュアスケート界を見つめ直す機会としていただければ幸いです。
観客席の空席が目立つようになった?現場の実感
チケット争奪戦の変化
フィギュアスケートの競技会(全日本選手権、NHK杯等)やアイスショーについては、毎回チケット争奪戦が繰り広げられることで有名です。
私は2012年頃からフィギュアスケート現地観戦をしていますが、年々チケットは取りやすくなっているように感じます。特にここ数年は絶対に行きたいけどチケットが取れない…ということはほとんどなくなりました。もちろん、チケット抽選に外れることはありますが、複数回のチケット販売を経て最終的には欲しいチケットを全て入手しています。
かつてのように「手に入らない」「抽選に全く当たらない」というほどではなくなりつつある印象です。そういった意味では、フィギュアスケートを現地観戦したいと思っている人が以前と比べて減っているというのは、感覚的にはそうだろうなと理解できます。
観客動員数の変化
実際の統計データを取ることはなかなか難しいものの、私の現地観戦時の感覚としても、座席が埋まりきっていない会場を見ることは増えたと思います。
毎年シーズンのスタートとして開催されている日本代表選手エキシビションであるドリームオンアイスでは、とくに平日公演においてかなりの空席が目立ちます。また、全日本選手権やNHK杯も多くの観客が入っているようには見えますが、一部座席において空席が残っています。
ただ、全日本選手権については、かつて12月23日が天皇記念日で祝日だったことは間違いなく影響しているでしょう。以前は祝日だったので現地観戦しやすかったですが、今は平日なのでなかなかそうはいきません。
とはいえ、会場の座席の埋まり具合から見ても、フィギュアスケートを現地観戦している人は減っているだろうというのも、感覚的に理解できるところはあります。
現地観戦が減少する理由
ライブ配信の充実
かつては、現地観戦せずにフィギュアスケートを観戦する手段として地上波テレビ放送が主流でした。しかし、放送局の都合によって、一部選手の演技しか放送しなかったり、有力選手のドキュメンタリー動画ばかり流していたり…ということもしばしば。
しかしここ数年は、ネット配信やオンデマンドサービスが充実してきたことで、ほぼすべての演技をリアルタイムかつ高画質で視聴できる環境が整いつつあります。
私も、以前は「生の演技を見たい」「テレビに映らない選手までしっかり見たい」という理由で頻繁に会場に足を運んでいました。現在も現地観戦を頻繁に行っていることは変わりませんが、全日本選手権の予選会であるブロック大会については、自宅でライブ配信を見るようになりました。
誰しもが事情があります。交通費や宿泊費をかけて、仕事の都合をつけて、家族にも話をして、遠方の大会に現地観戦しに行くよりも、自宅からリアルタイムで観戦するという方法もあるのです。
観戦スタイルは多様化しており、現地観戦者が減っているという理由だけでフィギュアスケート人気が低下していると決めつけるのはいささか早計だと言わざるを得ません。
高額なチケット料金
ここ数年、世界的な物価高の影響は生活のあらゆる面に及んでいます。食料品や光熱費、交通費などの価格が上昇する中、フィギュアスケート観戦に充てられるお金が減っていると感じる方も多いのではないでしょうか。
以前なら「フィギュアスケートを見に行きたいから多少無理をしてでもチケットを買う」という人がいたとしても、今はその「多少の無理」が難しくなっているのが現状です。無理して現地観戦するよりかは、安価な料金を支払って自宅からライブ配信を見るという選択肢を採るでしょう。
フィギュアスケートは音響や照明、リンク整備など、大会運営にかかるコストも非常に高い競技です。高いチケット料金を設定せざるを得ない面もあるでしょう。しかし、興行収益を追求するあまり、チケット高額化が進めば進むほど、若い世代や経済的に余裕のない層を遠ざけるリスクが生まれます。
今に始まった話ではありませんが、フィギュアスケートにおける永遠の課題でしょう。
スター不在が競技人気に与える影響?
スター頼みの危うさ
フィギュアスケートに限らず、多くのスポーツが「スター選手の存在」に支えられている側面は確かにあります。特定の選手が抜群の実績とカリスマ性を持っていれば、その選手を応援しようとするファンが一気に集まります。しかし、スター不在になると一気に競技自体の露出が減り、ファンが離れていくという現象は、長期的に見てスポーツが発展していくうえでは好ましくありません。
スター頼みでスポーツの人気を保とうとするのではなく、スポーツ自体の人気を高めるような取り組みをすべきではないでしょうか。
“スター不在”の捉え方
実は「スター不在」といわれる状況でも、よく見渡せば実力と魅力を兼ね備えた選手は多数存在します。
たとえば女子シングルでは、坂本花織選手が圧倒的な実績を残し、安定感ある演技を続けていますし、海外にもアナスタシア・グバノワ選手を始めとした才能ある選手が少なくありません。
男子では、イリヤ・マリニン選手の4回転アクセルを武器とした大技が話題をさらい、これを追いかける形で鍵山優真選手などが競い合う図式ができています。
それでも「スター不在」と言われてしまうのは、かつてのように “国民的英雄” と呼べるような選手が競技会場で一挙手一投足を注目される状況からは、一歩引いた形になっているからかもしれません。しかし、それは決して「魅力的な選手がいない」という意味ではないはずです。
選手たちの「個性不足」と時代背景
SNS時代のリスク管理
「昔のスター選手と比べると、今の選手は個性が薄い」という指摘もありました。たしかに、かつては大胆な発言をしたり、独特の言動で話題を集めたりする選手が目立っていました。しかし、今はSNS全盛の時代。選手自身が不用意な発言をすればたちまち炎上し、競技外の部分で批判を浴びるリスクも高まっています。
そのため、特に若い世代の選手たちは、幼いころからSNSの使い方に気をつけるよう指導を受けているケースも少なくありません。発言をコントロールし、できるだけ波風を立てないように振る舞うことが、むしろプロフェッショナルとして「当然の振る舞い」という意識が根付いているのです。
全体的な技術レベルの向上
国民的ヒロインとして絶大な人気を誇った浅田真央さん。天真爛漫な姿はもちろんですが、彼女をヒロインたらしめたのはやはりトリプルアクセルでしょう。当時、女子選手では歴代で片手で数えるくらいしか成功者がいなかったジャンプであり、彼女の代名詞となりました。
しかし、今ではトリプルアクセルを跳ぶ女子選手は決して珍しくありません。国際スケート連盟は「歴代〇〇人目のトリプルアクセル成功者」とカウントすることを止めてしまったほどです。
先日開催された2024年全日本選手権の女子シングルにおいて、トリプルアクセルを試みた選手の人数をご存じでしょうか?なんと5人です(島田麻央、渡辺倫果、中井亜美、吉田陽菜、岡万佑子)。
もちろん、技術レベルが向上した今でも難しいジャンプには違いありませんが、かつてのように歴代でも数名…というジャンプではなく、現実的に戦術として想定が出来るジャンプになりました。
全体的な技術レベルが確実に上がっているからこそ、選手は個性を出しにくくなっているように感じます。
まとめ:フィギュアスケート人気は本当に低下しているのか?
本記事では、フィギュアスケートの人気は本当に低下しているのか?という点について、いくつかの切り口で検討してきました。
まず、チケット争奪戦の変化と観客動員数に触れ、かつて入手困難だった大会のチケットが取りやすくなっていることや、一部の大会では席が埋まらない状況が増えてきたことを確認しました。
一方で、ライブ配信の充実や物価高によるチケット料金の負担増が観戦スタイルの変化を加速させていることを指摘しています。
さらに、「スター不在」がしばしば人気低下の原因とされますが、必ずしもそうとは言い切れない理由も浮き彫りになりました。確かに、特定のスター選手に人気が集中する構造はあります。
しかし、国内外には優れた選手が多数おり、“国民的英雄” と呼べるような絶対的存在が見当たらないからといって、競技そのものの魅力が失われたわけではありません。
むしろ、全体の技術レベルが向上し、ジャンプや表現力の面で新たな才能が次々と頭角を現していることから、多様な見どころが生まれていると言えるでしょう。
また、SNS時代を迎えたことで、選手たちは炎上リスクを回避するために言動をより慎重に行うようになっています。
「個性不足」と言われる背景には、こうしたリスク管理意識の高まりや、競技内での技術革新が激しいがゆえに大胆な個性が前面に出しにくくなった状況があるのかもしれません。しかし、この点も決して競技の魅力が減ったわけではなく、むしろ魅力は増しています。
総じて、観客席の空席増やチケットの取りやすさが「人気の完全な低下」を示すとは限らず、ライブ配信時代による観戦スタイルの多様化や物価高による観戦費用の負担など、複合的な要因が絡んでいることがわかります。
「スター」という言葉だけに注目するのではなく、競技そのものが持つ本来の魅力をいかに広く伝え、フィギュアスケートそのものに対するファン層を継続して築いていけるかが、今後のフィギュアスケート界における重要な課題となるでしょう。
スターの登場を待つのではなく、フィギュアスケートというスポーツに対するファンを増やすということが重要ではないでしょうか。